労働、娯楽、あるいは観光における動物利用の倫理は、多くの場合、動物権や動物福祉といった規範的概念に基づき、普遍的な用語で語られる。しかし近年の学術研究において馬の乗用と象の乗用の比較的な扱いを検討すると、顕著な非対称性が浮かび上がる。西洋の文脈では、馬に乗ることはしばしば当然のものとされ、馬術文化の一部として称揚されるか、あるいは人間と動物のパートナーシップの場として価値づけられる。それに対して象乗りは、ほとんど無条件に否定され、残酷、後進的、あるいは救済不能と描かれる。この非対称性は、動物そのものの特性だけでは説明できない。なぜなら馬も象も、大型で知的かつ社会的な哺乳類であり、人間とともに働いてきた長い歴史を共有しているからである。むしろこの分岐は文化的バイアスを反映しており、それはユーロ=アメリカ的な歴史や動物利用の象徴地理に根ざしている。
ヨーロッパや北米では、馬は国民的神話や余暇文化の中に組み込まれている。中世の騎士道からカウボーイのフロンティアに至るまで、馬術の伝統は自由、高貴さ、さらには環境調和の表現として自然化されてきた。乗馬はスポーツ、芸術、あるいは治療的実践として再解釈され、馬は近代性や文明の物語と結びつけられる。それに対して象は「異国の他者」として位置づけられる。動物園、サーカス、観光キャンプにおける象の存在は、多くの場合、スペクタクルや支配といったオリエンタリズム的想像力を通じて解釈される。この枠組みの中で、象乗りは搾取の象徴となり、アジアの風景に投影され、外部から裁かれることになる。ドナ・ハラウェイが霊長類学批判1で示したように、科学的記述は決して中立ではなく、文化的想像力や地政学的歴史、そして研究者自身の立場性によって形作られる。ここでも同様の構造的バイアスが働いており、馬は西洋文化の内部で家畜化される一方、象は異国的な存在として印づけられ、道徳的精査の対象となる。
この文化的バイアスは学術記録にも反映されている。過去10年間の査読済み動物科学および保全関連の論文を予備的に比較する2と、ヨーロッパや北米に拠点を置く第一著者は、労働や観光における象の利用を否定的に描き、苦痛や残虐さ、禁止の必要性を強調する傾向が強い。一方で、アジアの研究機関に所属する著者、特に歴史的に人と象が共に生き働いてきた国々では、福祉改善、共生戦略、あるいは文化的・経済的文脈に重点を置く傾向が見られる。この分岐は単純な東西の倫理的二分法を意味するのではなく、むしろ研究アジェンダ、資金構造、出版ネットワークが特定の枠組みを優先することを明らかにしている。西洋の著者は主として西洋の読者に向けて、権利ベースの批判を前面に押し出す一方、アジアの研究者は、地域の現実に共鳴する、より実践的で文脈に敏感なアプローチを取る場合が多い。
馬と象の対比は、このように「普遍的」とされる倫理判断が特定の文化的レンズによって形作られる事例研究となる。何が許容可能な利用、パートナーシップ、あるいは虐待とみなされるかは、種の特性そのものによって決まるのではなく、歴史的に位置づけられた物語や立場性によって規定される。西洋のアイデンティティに統合された馬は全面的な非難を免れる一方、この文化的枠組みの外に置かれた象は、道徳的警鐘の標的となる。ここで象観光における実際の福祉問題を否定するのではなく、選択的な道徳化が、馬、犬、あるいは家畜に対するユーロ=アメリカ的文脈での集約的利用といった、より広範な動物利用の構造を覆い隠しうることを強調したい。
こうした非対称性を超えていくためには、より関係的で応答的な倫理が必要である。それは普遍化された判断を拒み、人間と動物の関係的な絡まり合いの生きられた文脈を真剣に捉えるものだ。そのようなアプローチは、次のような問いを立てるだろう。乗用、労働、あるいは伴侶関係は、いかなる条件の下で可能となるのか?ケア、強制、相互依存は、異なる景観においてどのように交渉されているのか?そして、植民地主義的な判断のヒエラルキーを再生産することなく、文化的差異をどのように認識できるのか?課題は、ある実践を本質的に良いあるいは悪いと宣言することではなく、位置づけられた歴史、多種間の関係、そして動物利用がどのように想像され評価されるかという不均等なグローバル政治に注意を払い続けることにある。
- ドナ・ハラウェイ『霊長類の視覚』(1989)について
ドナ・ハラウェイの Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science(1989)は、フェミニスト科学論の画期的著作であり、霊長類学の歴史を批判的に検討するものである。ハラウェイは、霊長類学は「自然」の真理を客観的に発見する営みではなく、むしろ文化的・政治的実践であると論じる。彼女によれば、霊長類学者によって生産される知は、ジェンダー、人種、植民地主義の文脈と深く結びつき、それによって形作られている。
主要な論点:
霊長類学は物語としての科学:科学的記述は物語であり、それは特定の文化的レンズを通じて構築され、既存の社会的ヒエラルキーを強化することが多い。初期の研究では、西洋的な家父長制や社会秩序の観念が霊長類の群れに投影されていた。
猿・類人猿の文化的アイコン化:霊長類は西洋文化において人間の起源や本性への不安や欲望を投影する対象となり、政治的・社会的アジェンダに奉仕する象徴として用いられてきた。
ジェンダーと科学:男性研究者と、ジェーン・グドールやダイアン・フォッシーのような女性研究者の視点の違いに注目し、科学的枠組みの中でも異なる方法論や関心が現れることを示す。
「自然」の脱構築:自然は科学が単に発見するものではなく、科学的言説と実践を通じて構築される。霊長類について「わかっていること」は、文化的に特定された見方や物語の反映にほかならない。 ↩︎ - 2013年から2023年にかけて Journal of Zoology、Oryx、Animals、Conservation Biology といった学術誌に掲載された査読論文を調査したところ、地域的な偏りが確認された。西洋(主に英国、米国、西ヨーロッパ)の所属を持つ第一著者による論文では、象観光に言及するもののおよそ 3 分の 2 が、残虐性や福祉違反、倫理的不適合を強調する否定的な枠組みを取っていた。一方、アジア(タイ、インド、ラオス、カンボジア)の所属を持つ第一著者による論文の多くは、福祉基準、管理上の課題、文化的統合を強調しており、全面的な否定は少なかった。これらの観察は統計的というより質的で予備的なものであるが、論調や評価枠組みにおいて一貫した地域的差異が存在することを示唆している。 ↩︎



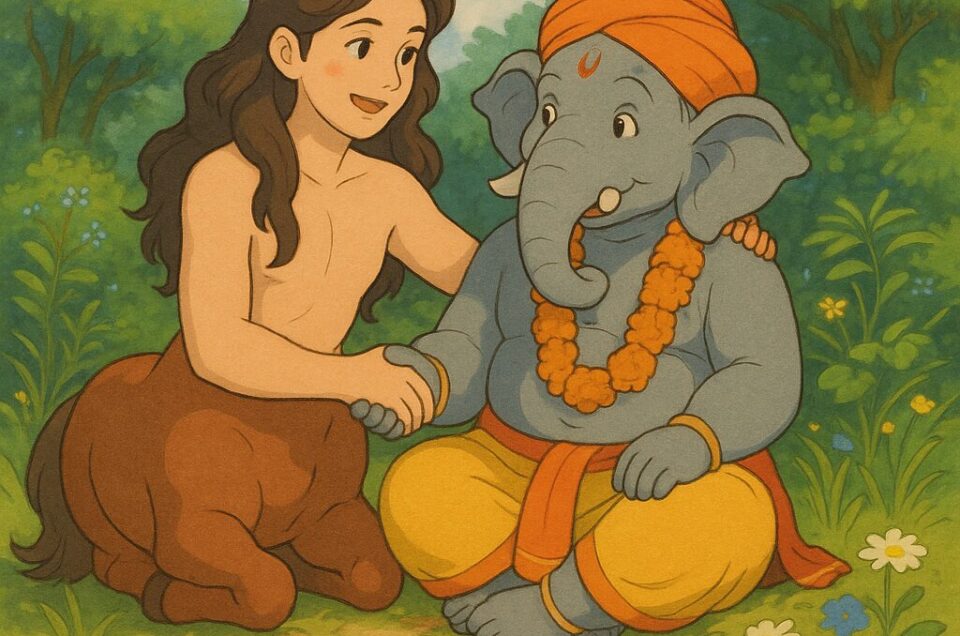
![[1] Q: 観光に従事している象は野生の象ですか、それとも家畜の象ですか?](https://manifatravel.com/wp-content/uploads/2023/03/elephant-vet4-780x636.jpg)
![[2] Q: 象に乗るのは危険ですか?](https://manifatravel.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_5363-960x636.jpg)

